🌙 導入
「“解像度が低い”って言われた……。」
ある日の会議後、上司の冷静な一言が頭から離れませんでした。
報告したつもりが「結局どう動けばいいのか分からない」と返される。
プロジェクトリーダーになりたてで技術的に聞いたことしかない状況の報告なんて霧のように曖昧になるに決まってる。
帰宅途中の電車で「このままじゃリーダー失格だ」と胸の中で赤信号が点滅しました。
それから改善のために、いろんな本や研修に手を出しました。
ロジカルシンキング、ピラミッドストラクチャー、仮説思考……。
気づけば積読タワーができていて、部屋がちょっとしたビジネス書図書館に。
そんな中で出会ったのが『戦略的勉強法』でした。
📖 本との出会い

今回の出会いはかなり偶然。
翔泳社公式通販 SEshopのポイント50%還元セール で本書が対象になっていたんです
(キャンペーンURLはこちら:SEshop キャンペーン)。
「半額?ポイント還元?これはもう運命でしょ」と、紅茶を片手に即ポチ。
こういうセールって、財布より心を動かしてきますよね。
著者は、勉強法やスキルの整理を分かりやすくまとめてくれるタイプで、ジャンルとしてはビジネススキルの基礎を広く学べる内容。
とりわけ「コンセプチャルスキル」と「ヒューマンスキル」に分かれていて、今回は前者を重点的に読み込みました。
💡 気づきの瞬間
心に刺さったのは 「仮説思考は『点』ではなく『円』で考えよう」 というフレーズ。
私は普段、プロジェクトリーダーとして 複雑な問題を理解し、ベストな解決策を意思決定する立場 にあります。
コードを書くのも大事ですが、それ以上に必要なのは 「情報を整理し、人に伝え、チームを動かす」力。
コンサルタントほど難解ではないにせよ、“考える力”は不可欠。
そんな中で、仮説を立てずに「なんとなく」で会議に挑んでいた過去の自分を思い出し、背筋が凍りました。
仮説 → 検証 → 修正 を繰り返し、サイクルのように磨いていく。
この当たり前の仕組みが、自分には欠けていたのです。
ロジカルシンキングだけでは足りない
ロジカルシンキングで課題の見え方は少しずつ分かってきました。
しかし、どこかに 「これじゃない感」 が残っていたんです。
そこで効いたのが 仮説検証の考え方。
「前回の情報を踏まえて、次なる一手は……?」と考える習慣が、曖昧さを減らしてくれました。
先が読めないプロジェクトでは、何が起こるか分からない。
試さなければ気づけないことも多い。
仮説を出しては修正する、そのリズムこそが“曖昧リーダー脱却”の第一歩でした。
🤖 AI時代の気づき
最近はAIを使う機会も増えました。文章生成や分析に役立ちますが、
AIが出してくるのはあくまで“候補のひとつ”に過ぎません。
- 正解とは限らない
- 鵜呑みにすると危険
- 最後の「検証」は人間が担保する必要がある
AIは便利な補助輪。
でも、ゴールにたどり着けるかを判断するのは人間の仮説検証力 だと痛感しました。
本書を読んで、そのスタンスを改めて心に刻んだ瞬間でした。
🚀 試してみたこと
✅ 成功体験:仮説を持ち込む勇気
次の週、資料を準備しながら「遅延の原因はAかBでは?」と仮説を3つほど書き出しました。
会議中に提示して、メンバーの意見で修正していくと、自然と「じゃあこうしよう」と結論が出ていく。
会議中の上司の不安そうな質問がなくなり、十分伝えられることができるようになったと実感。
❌ 失敗体験:暴走する仮説
一方で、「とにかく仮説を速く回そう」と意気込みすぎて、見当違いな仮説を出して赤っ恥をかいたことも。
しかも睡眠を削って準備したせいで、会議中に軽くフラフラ。
まさに「効率を求めて効率を落とす」パターンでした。今では笑えるけど、当時は冷や汗ものでした。
🌓 変化と成長
読む前は、報告のたびに「結局どうすれば?」と聞かれ、心の中で萎縮していた。
読んだ後は、たとえ仮説が間違っていても「まずこう考えました」と提示できるようになり、会議の雰囲気が前向きに変わりました。
特に大きかったのは、自分の中で「コンセプチャルスキル=論理的に考え整理する力」が“必須スキル”として輪郭を持ったこと。
今まで読んできた本や研修での学びがバラバラに積み上がっていたのが、この本を“総集編”のように読むことで整理されて安心感につながりました。
🎯 読者への提案
この本をおすすめしたいのは:
- 会議や報告で「フワッとしてる」と言われがちな人
- プロジェクトリーダーや若手管理職で、思考整理や意思決定に不安がある人
- 勉強はしてるけど「今のやり方でいいのか?」と迷っている人
逆に、すでにフェルミ推定や仮説思考をバリバリ実践しているコンサル経験者には物足りないかもしれません。
でも、これを読んで「学び方の地図」を手に入れれば、次に何を勉強すればいいのかもクリアになります。
実際、私は「細谷功氏のフェルミ推定の本を次に読もう」と決めました。
あなたも、今の勉強法に少しでも迷いがあるなら、一度立ち止まって“全体像”を確認してみてはいかがでしょうか?
🌱 まとめと余韻
まとめると、『戦略的勉強法』は単なる勉強法の紹介ではなく「思考をどう扱うか」の基礎を整える一冊でした。
- 仮説を立てることは、完璧じゃなくてもいい
- サイクルを速く回すことで思考は磨かれる
- 既に学んできたことを“総集編”の形で再確認できる
紅茶で例えるなら、蒸らし時間を少し意識するだけで味わいが変わるようなもの。思考もほんの少しの工夫で解像度がグッと上がります。
最後にユーモアを一つ。
「仮説が外れて赤っ恥をかいたときは、紅茶のティーバッグを間違えてほうじ茶にしたと思えばいい。香ばしい発見が待っているかもしれません。」
今日も一杯の紅茶と一つの仮説で、解像度を上げる一日を始めましょう。
次回はヒューマンスキルで容量のいいリーダーへのポイントを書いています!

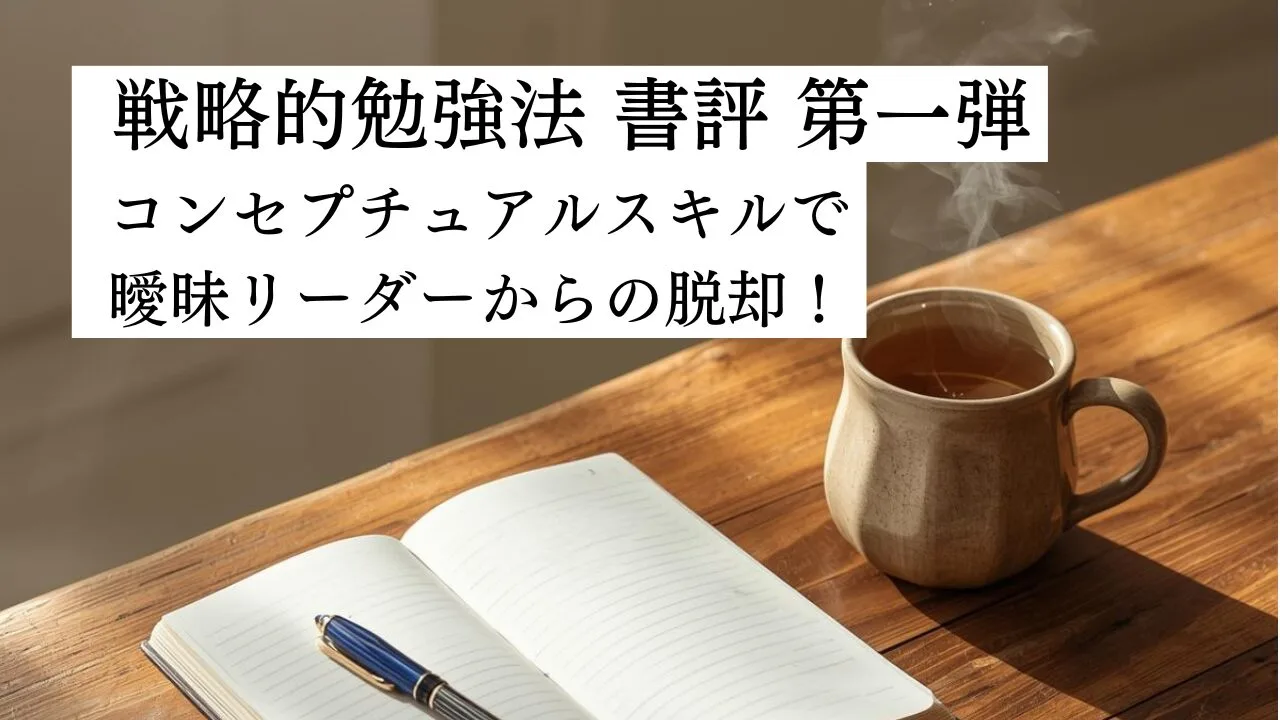
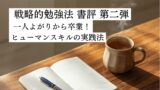


コメント