✨はじめに
読書が趣味だと言えるほどではないけれど、気になる本にはつい手を伸ばしてしまう——そんな私が最近読んだのが、モーティマー・J・アドラー著『本を読む本』です。

この書籍は、単なる読書術の本ではありません。「本を読む」という行為をいかに深く、効果的に行うかを体系的に解説した一冊であり、1940年ごろに書かれた古典的な名著です。日本でも長く読み継がれてきました。
とはいえ、正直に言えば最初の印象は「難しい!」の一言。何度も読み進めては理解できず、気づけば寝落ちしていることも……。それでも、読了後には「読んでよかった」と思える深い学びがありました。
このブログでは、『本を読む本』を通じて私が得た気づきや読書に対する向き合い方の変化について、等身大の感想を交えながら綴っていきます。
😵読むのがしんどかった理由
『本を読む本』を手に取ったとき、すぐに「これは簡単には読めないな」と直感しました。その理由はいくつかありますが、大きく分けて以下の二点が特に印象に残っています。
🌀難解な内容と古典的な例
まず挙げたいのは、書かれている内容の難しさです。文章は決して平易ではなく、言い回しもどこか抽象的。しかも例として出されるのが、1940年頃に一般的だったシェイクスピアの作品や古典的な文献ばかり。たとえば「みんなが知っているシェイクスピアのXXでは…」と当然のように語られても、現代に生きる私にとっては、その前提すら分からない状態でした。
例が自分にとってピンと来ないというのは、思った以上に読みづらさに繋がるものです。著者の伝えたいことが理解できないままページが進んでいき、読書体験としてはかなりの苦戦を強いられました。
👓小さな文字と読書スピードの課題
もうひとつの壁は「物理的な読みづらさ」でした。書籍の文字が小さく、ただでさえ難しい内容なのに、目で追うのも一苦労。ページをめくるごとに集中力が落ちていく感覚があり、正直なところ、「読書が好き」と言い切れない自分にとっては、かなりつらい体験でした。
この読書体験を通じて、「まだまだ自分の読書技術は足りていない」と強く感じました。しかし、その自覚があったからこそ、本書に書かれていた「読書の段階」や「本の選び方」といった部分が、逆にとてもリアルに響いたのです。
🔍印象に残った学び①:点検読書の重要性
『本を読む本』で最も印象に残ったのが、「点検読書」という考え方でした。これは、読書の前段階として、本の全体像を短時間でつかむための読み方です。
⏱️タイパ・コスパ重視の現代にぴったり
現代では「タイムパフォーマンス(タイパ)」や「コストパフォーマンス(コスパ)」が重視される時代です。限られた時間の中で、いかに自分にとって価値のある情報を得るかが問われます。
私は読むのが遅いほうなので、選ぶ本を間違えたときの「時間の損失」がとても大きく感じていました。そんな中で「点検読書」という手法に出会い、「読む前にその本が本当に自分に必要かを見極める」ことの大切さに気づかされました。
📝実践してみた点検読書
実際に私は、書店で気になった本があったとき、まず「目次」をしっかりと見るようになりました。以前は目次はほとんど見なかったのですが、本の構成や論理展開が明確に分かると、内容の全体像を早く把握できるようになります。
また、「はじめに」や「終わりに」、「章末のまとめ」などにも注目するようになりました。そこには著者が伝えたいことのエッセンスが詰まっていて、短時間で本の核をつかむことができます。
さらに、「著者がどんな人なのか」も意識するようになりました。専門家なのか、実務家なのか、あるいはどんな読者層を想定しているのか――そういった情報が分かれば、自分に合った本かどうかの判断材料になります。
📦本の断捨離にも効果を実感
最近では、読まなくなった本をメルカリで手放すことが増えました。周囲から勧められて読んでみたけれど、正直あまり響かなかった本が多く、「2回目はないな」と感じることもしばしば。
点検読書をしていれば、最初から「今の自分に必要な本かどうか」を判断できたかもしれません。おすすめされた本でも、自分のニーズやタイミングに合っているかを確認することが、無駄な読書を減らすコツだと実感しました。
🧠印象に残った学び②:分析読書での読み方
点検読書によって「読むべき本」を選べるようになったら、次に大事なのが「どう読むか」です。ここで登場するのが『本を読む本』のもう一つの大きな柱、「分析読書」という読み方でした。
🤯読書が頭に入らない理由とは?
読書中、「全然頭に入ってこないな」と感じることはありませんか?
私もまさにそうでした。何度も同じページを読み返しても理解が進まず、途中で諦めたくなることもありました。
そんな中で気づいたのが、「筆者は何を伝えたいのか?」という視点を持つことの重要性です。本は読者に分かりやすく伝えるために、たくさんの言い回しや具体例を用います。その結果、「結局この章で何が言いたかったんだっけ?」ということがぼやけてしまうのです。
📖著者の意図を意識する「分析読書」
分析読書では、「この章で筆者が本当に伝えたいことは何か?」という問いを常に持ちながら読み進めます。これによって、本の内容がただの情報の羅列ではなく、明確な「メッセージ」として頭に入ってくるようになります。
しかも、点検読書を先にやっていることで、全体構成や章の役割が見えている状態になります。そのため、「この章は全体の中でどんな位置づけなんだろう?」という視点も持ちやすくなり、理解が一段と深まります。
📈読書の「質」が上がる実感
分析読書を意識するようになってから、以前よりも読書が頭に残るようになったと感じています。ただ漫然と読むのではなく、「筆者の考えを理解しようとする読み方」をするだけで、同じ本でも得られる情報量が格段に違ってくるのです。
これはまるで、読書が「作業」から「対話」に変わったような感覚でした。「著者が今、私に何を伝えようとしているのか?」を考えながら読むと、本との距離がグッと近くなったように感じます。
📝おわりに
『本を読む本』は、決して読みやすい本ではありませんでした。古典的な文体や例の数々に苦戦し、何度もページをめくっては立ち止まり、そのたびに読み直して……。けれど、そうした苦労の末に得られた「読書に対する視点の変化」は、私にとって大きな財産となりました。
点検読書によって、本を選ぶ目が養われました。「なんとなく読む」から「目的をもって読む」へと意識が変わり、読む前に目次や著者の情報、構成を見る習慣がついたことで、読書の質が確実に向上しました。
そして分析読書では、「筆者が何を伝えようとしているのか」を意識することで、これまで以上に深く内容を理解できるようになりました。ただ情報を受け取るだけでなく、自分の頭で考えながら読むということを、この本が教えてくれました。
読書という行為は、人生のあらゆる場面で役立ちます。自己成長のためにも、仕事のスキルアップのためにも、本を「どう読むか」は非常に重要なテーマです。もしあなたも「読んでいるのに頭に残らない」「どの本を選べばいいか分からない」と感じているなら、ぜひ一度『本を読む本』を手に取ってみてください。
きっと、読書に対する考え方が変わるはずです。

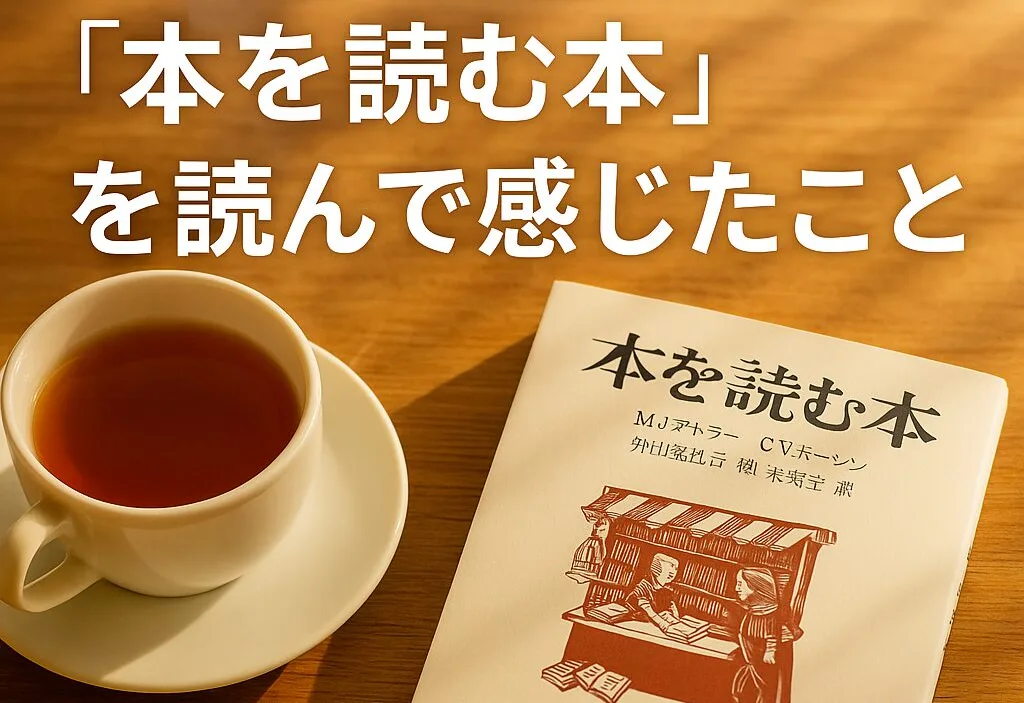


コメント